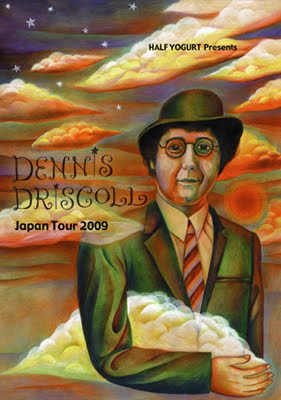まだまだイ・ランについてのエントリーが続きます。どうぞおつき合いください。
さて、7月に地元・韓国でリリースされた彼女のセカンド・アルバム『神様ごっこ』ですが、なんと発売から数週間でレーベル在庫が底を尽きたという嬉しいニュースが入りました。前作『ヨンヨンスン』も2,000枚以上のセールスを記録したようですから、となると今回の初回1,000部は在庫切れで当然なのかもしれません。でも、人口も(韓国の人口は約5千万人、日本の半分以下です)、そして自ずと音楽マーケットの大きさも日本とは格段に異なる隣国でそれだけ広く深い支持をイ・ランが受けていることは、とても頼もしく励まされる気持ちがしています。
特に今回、読む者/聴く者を魅了した驚くべきは彼女の言葉の力だったに違いありません。韓国版で90ページを超える『神様ごっこ』のエッセイは、あいだに収録曲10曲の歌詞を織り込みながら、彼女のこれまでの歩みや家族、その人間観や世界観、創作の裏側や死と生への執着等々について深い、かつユーモラスな洞察に満たされます。この数週間、僕自身が何度も何度も何度も何度も原稿を読み返して校正を重ねてきましたが、その度に彼女の機転に救われ続けました。このいわば「小説版イ・ラン」のとんでもない面白さ、ぜひご期待いただければと心から願っています。
と、ここで『神様ごっこ』の内容の一端を覗いてもらうために、カーリー・ソルの頼もしいラフくんことキム・ハンソル氏に協力していただきながら、韓国版のプレスリリースを訳出してみました。エッセイからの抜粋も下に添えてありますので、どうぞ読んでみてください。なお、この韓国版プレスリリースは、どちらかというと『神様ごっこ』のシリアスな面、ペシミスティックな面を強く捉えていますが、もちろんそれだけではないことは、またあらためてご紹介できたらと思っています。引き続きどうぞお楽しみに。

イ・ランはファースト・アルバム『ヨンヨンスン』を出したあと、誰にも予測できないようなレコードをつくろうと考えていた。弘大(ホンデ)に広がっている「ささやかな日常」のアコースティック音楽に反旗を翻し、哲学と死を語るレコードをつくりたかった。軽い時代に最も重いレコードを。なぜなら私たちの生活は重苦しく、死でぎっしりと埋まっているから。
イ・ランにとってニュー・アルバムとなる『神様ごっこ』は、現在さまざまな分野で活躍中の最高の演奏者を迎え、イ・ランがいちばんくつろげる場所である雨乃日珈琲店でレコーディングされた。楽器を持って店に集まり、営業が終わってから明け方まで録音するのだ。普通のスタジオとは違い、リラックスできるので自然体となり、音響にも雨乃日珈琲店ならではの特性がにじみ出た。ひとりでMacBook を使って録音した『ヨンヨンスン』と違い、『神様ごっこ』はキム・ギョンモのプロデュースの下、最高のクオリティーを目指して制作された。チェロのイ・ヘジ、ドラムスのチョ・インチョル(404)、ベースのイ・デボン(ソリミュージアム)の3人を核として、特に締め切りを設けずに録音が続けられる。完成まで3年もかかったのはそのためだった。
また、今回のアルバムは書籍の形をとっていて、付属するカードに記載されたパスワードでアルバム(全10 曲)をダウンロードする仕様でCD の発売は予定されていない(注:日本国内盤はCD 仕様)。かように、CD プレイヤーが不要となっている韓国の現状を考慮して、リリース形態も新しい試みとなった。エッセイの中でイ・ランは「死にたい」と口にする人を無視せず、「なぜ死にたいのか」と問うこと、
そして長い対話をする必要があることを書いている。しかし「死にたい」とこぼしてしまった人は覚えているはずだ。そういった話題には往々にして「そんな話はしちゃだめだよ」とか「苦しんでいるのはあなただけじゃない」というような返事が返ってくることを。
そして長い対話をする必要があることを書いている。しかし「死にたい」とこぼしてしまった人は覚えているはずだ。そういった話題には往々にして「そんな話はしちゃだめだよ」とか「苦しんでいるのはあなただけじゃない」というような返事が返ってくることを。
人生を賛美する歌は誰もが好きだが、死についての歌は暗く、消費されてしまう。アイドルは爆発するような美貌とスタイルを誇りながら、輝くものについて歌う。一方、イ・ランは「輝くものは山ほどある/その中で本物を見極めるんだ」と歌うEXO(訳注:韓国と中国で活動する男性アイドル・グループ)の「Call Me Baby」を聴きながら、勇気をふりしぼって「死にたい」という言葉を発した人の長い夜を繰り返す。本当の気持ちを否定されても明日になったらまた偽物の光を輝かせ、生きることがすべてであるかのように賑やかな道へ踏み出していく彼ら。
「死にたい」と口にするのは必死に生きるためなのに、そういう人に限って死んでいってしまう。死を知らないふりをする人は、あとからやってくる曖昧な罪悪感を忘れようとまた死を無視し続ける。そうやって我々は死んでいき、死についてなんの配慮も準備もないまま、お互いの死を相手にせず死に満ちた人生を生きていくのである。

『神様ごっこ』からの抜粋
3年前、蘆原(ノウォン)区の小学5年生の子どもたちを対象に、作曲の授業をしたことがある。私の目標は、子どもたちと一緒に童謡をつくることだった。それまで私が考えていた童謡は「明るく朗らかでかわいい」もの。花が咲きトンボが飛び子どもが走りまわるようなものだった。
でも、いざ授業がはじまってみると、子どもたちが聞かせてくれる話はまったく違うものだった。子どもたちは私に、生きるうえでのつらさや無気力、死について話した。死にたいのは山々だけど、ただ「生きてるから生きるだけ」と話す子どもさえいた。誰もに憎い友達がひとりはいて、したくないことは数え切れないほどあった。持ち物を利用して音を出すワークショップをしたとき、いきなり教科書で机を叩き出した子どもがいた。大きな音を出せば出すほど教科書がぼろぼろになって、その子は大きな喜びを感じているようだった。あとで知ったことだが、それはその子が最も嫌いな先生が教える科目の教科書だったらしい。
その瞬間、私は悟った。やはり私も小学生のころ、花やトンボのことを考えながら一日を過ごしたわけではなかった。私は下校途中の道に落ちている何かの破片を拾い集めていて、その残りの欠片を持っている誰かが現われて、私をこの乞食みたいな日常から救ってくれることを願っていた。私の部屋の机の上に敷いた薄いガラスには、大人になったら殺したい人の名前が書いてあった。
結局、私と子どもたちは、嫌いなものや疲労感、そして死についての曲をつくった。